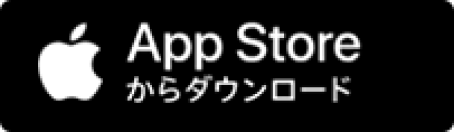INDEX
カーボンニュートラルの実現に向けて注目される電気自動車(以下、EV)ですが、コスト面でガソリン車とどちらがお得なのかと迷う人は多いでしょう。車両の維持には購入価格だけでなく、長期的なコストも影響します。
EVは、走行コスト(充電料金)やメンテナンス費用がガソリン車よりも抑えられる傾向があります。走行距離や使用年数によってはお得になる可能性もあります。
当記事ではEVとガソリン車、それぞれにかかる費用や、税制上の優遇、利便性を徹底的に比較し、それぞれの項目に分けて解説します。
車両の購入にかかるコストを比較
車を購入する際、車両価格は大きな判断材料となります。ここではEVとガソリン車の購入費用を比較しました。EVの購入にはCEV補助金(国からの補助金)や、お住まいの自治体から補助金が受けられます。
①軽自動車クラス
| 車種 | メーカー希望小売価格 |
| 日産 サクラ X | 259万9,300円~(税込) |
| 日産 ルークス S | 163万7,900円~(税込) |
(2025年5月時点の公式サイトによる情報)
②普通車クラス
| 車種 | メーカー希望小売価格 |
| 日産 リーフ | 408万1,000円~(税込) |
| MAZDA2(15SPORT) | 208万3,400円~(税込) |
(2025年5月時点の公式サイトによる情報)
- 結論
車両購入価格は、EVがガソリン車より高額です。
①軽自動車クラスでは約100万円の差
②普通車クラスでは約200万円の差
上記の価格の違いがありました。しかしEVは補助金が交付されるため、初期費用はもう少し抑えられる予想です。補助金については、次項で解説します。
EVの維持にかかる費用についてはこちら
電気自動車の維持費はどのくらい?補助金からランニングコストまで徹底解説
車両購入時に受けられる補助金
EVの購入時には、国や自治体から補助金を受けられます。ここでは、車両購入時に利用できる主な補助制度や申請のポイントをまとめました。
EV
EV購入時に受けられる公的機関からの補助金には、国が交付するCEV補助金と、お住まいの地域からの補助金の2種類があります。それぞれについて、以下で詳しく解説します。
CEV補助金
EVを自家用として新車で購入する場合、2025年度のCEV補助金は最大85万円です。加えて、車両製造にグリーンスチール(環境負荷の少ない鉄鋼)を使用するなどGX(グリーントランスフォーメーション)推進の要件を満たす車両には、最大5万円の加算措置があります。条件を満たすと、合計で最大90万円の補助が受けられます。
補助金の対象となる車両は、バッテリーEV(以下、BEV)、プラグインハイブリッドEV(PHEV)、および燃料電池車(以下、FCEV)で、ハイブリッド車(HEV)は対象外です。
なお、CEV補助金を受けるためには、納車日を含む1ヶ月以内に申請が必要であるほか、購入した車両を4年間継続して保有することが義務づけられています。これらの条件を事前にしっかり確認しておくことが重要です。
自治体からの補助金
お住まいの地域によっては、国から交付されるCEV補助金に加えて、地方自治体が独自に実施している補助金制度があります。
例えば、東京都では環境施策の一環として、条件を満たすEVに対し最大100万円の補助金制度が整備されています。国と自治体の補助金を併用すれば、EVの導入にかかる初期費用を大幅に抑えることが可能で、より手軽に環境に優しいモビリティを選択できるでしょう。
お住まいの地域によって補助金額は変わるため、利用できる補助制度を確認しておくことをおすすめします。
EV購入の補助金は東京都でいくらになる?ガソリン車よりもお得?
ガソリン車
ガソリン車では、EVのような公的な補助金制度はありません。これは、政府がCO2排出量の削減や地球温暖化対策の一環として、より環境に配慮した車両の普及促進を目的に補助制度を設けているためです。
EVに対する補助金は、一般的にEVの車両価格が高めであることや、インフラ整備が進行中であることを背景に、初期導入のハードルを下げることも目的となっています。一方、化石燃料を使用してCO2を排出するガソリン車は、環境負荷が大きいため補助金の支給対象とはならず、今後もその方針は続くでしょう。
- 結論
補助金の対象となるEVは、ガソリン車と比較して経済的な面で有利な購入条件が適用されているといえるでしょう。国や自治体からの補助金制度により、実質的な車両価格が大きく引き下げられるため、初期費用の負担を軽減できる点が大きな魅力です。

走行にかかるコスト
EVとガソリン車の最大の違いは動力源です。ここではそれぞれの走行にかかる充電料金代とガソリン代の違いを解説します。
EV
電気を動力源として走行するEVは、充電にかかる料金が走行コストとなります。EVの充電方法は、主に2種類に分けられており、自宅でゆっくり行う「普通充電」、もうひとつは外出先で短時間に多くの電力を補給できる「急速充電」です。ここでは、それぞれの特徴と利便性をまとめました。
普通充電料金
EVを自宅で充電する場合の電気代は、多くの家庭で月2,000〜3,000円台に収まることが多いです。外出先での普通充電器は、自動車メーカーなどの充電カードやアプリに登録し、月額料金を支払ったうえで、1分につき1.54~4.95円の充電料金を支払う方法が一般的です。
また、カードやアプリの登録なしでビジター利用ができる充電器もありますが、充電料金は割高になる傾向です。 Myプラゴの「普通充電バリュー」では、選択した1施設において、月額1,980円(税込)で月600分(1回あたり最大300分)まで利用可能です。
用語辞典:普通充電
急速充電料金
外出先の急速充電は、普通充電と同じように充電カードの月額料金を支払ったうえで、分単位の料金を支払うことが一般的です。急速充電料金は普通充電よりも電力量が多いため、1分につき27.5~38.5円が相場となります。
急速充電にもカードやアプリの登録なしでビジター利用ができる充電器がありますが、料金は割高です。
急速充電は「急速充電バリュー」(月額3,980円・税込)で、普通充電600分+急速充電150分(1回最大60分)まで利用可能です。
用語辞典:急速充電
ガソリン車
ガソリンの価格は原油相場の高騰を受け、ここ数年値上がりしています。1リットル当たりの価格は以下の通りです。(2025年5月現在 参考:gogo.gs)
| レギュラー | 180.5円 |
| ハイオク | 191.5円 |
レギュラーガソリンを燃料とする例として、燃費20.3km/LのMAZDA2で月1,000kmを走行した場合、レギュラーガソリン(180.5円/L)でおよそ8,891円かかります(2025年5月時点)。
- 結論
充電代(月3,000円)よりもガソリン代(月8,891円)が5,891円高くなりました。充電料金はガソリン代より低価といえます。(2025年5月現在)
EVの充電料金についてはこちら
電気自動車の充電料金完全ガイド:自宅充電からスタンド利用まで徹底解説

充電拠点 vs 給油所—ネットワーク規模比較
EVもガソリン車もそれぞれ充電や給油が不可欠です。いつでも手軽に燃料を補給できることは、車を維持するうえでのメリットといえるでしょう。
ガソリン車が専用のスタンドで給油するのに対し、EVは商業施設やディーラー、SAやPAなどに設置された充電器を使用できます。
EV
商業施設や高速道路のSA・PA、公共施設の駐車場など、外出先に設置されているEV用の充電器は、全国で2万5,862拠点(2025年5月末時点)。そのうち短時間でバッテリー容量の大部分を充電できる急速充電器の数は、1万2,832口です。(2025年5月末時点)
充電ステーションは、EVユーザーの利便性を高めるために年々整備が進められており、都市部から地方まで幅広く展開されています。
ガソリン車
全国におけるガソリンスタンドの店舗数は、現在2万7,407店となっています(2024年度末=2025年3月時点)
ガソリン車には、ガソリンスタンドが不可欠です。しかし近年は、EVの普及やガソリン貯蔵タンクの改修義務の強化により、徐々に減少傾向となっています。
- 結論
ガソリンスタンドの数は毎年約2~3%のペースで緩やかに減少しています。ガソリンスタンドにEV充電器を併設する店舗も徐々に増えてきました。EV充電器は、経済産業省が2030年までに30万口設置することを整備目標として掲げています。今後はさらにEVの充電が便利になるでしょう。
自動車税
車を維持するうえで欠かせないのが自動車税です。4月1日時点のオーナーに毎年課税されます。
EV
EVの自動車税は一律2万5,000円です。排気量がないEVは、すべて1,000cc以下とみなされます。 EVは新規登録翌年度から12年間、約75%の減税が受けられ、年額6,250円になります。仮に8年間使用した場合、合計5万円の支払いです。
ガソリン車
ガソリン車は排気量によって税額が異なりますが、MAZDA2 (1,500cc)の場合 3万500円です。(2019年10月以降に新規登録した車両の場合)
- 結論
車両を8年間使用した場合、ガソリン車で支払う自動車税の合計金額は(MAZDA2の場合)24万4,000円になります。一方、EVは5万円です。自動車税は、EVの方がガソリン車よりも19万4,000円お得になります。
自動車重量税
自動車重量税は、車両の重さに応じて課される税金です。新車購入時や車検の際にまとめて納付します。EVとガソリン車の自動車重量税の違いは、以下のとおりです。
EV
EVでは、車検時に支払う自動車重量税が環境負荷の少ない車両として「エコカー減税」の対象となり、優遇措置を受けることができます。
具体的には、新車登録から最初の車検、そして2回目の車検までの計5年間、自動車重量税が非課税となり、支払いが免除される制度です。エコカー減税の詳細や対象条件は、年度や制度の見直しによって変更される可能性があるため、最新情報を確認することも重要です。
ガソリン車
EVで免除になる自動車重量税は、ガソリン車では車の重量0.5トンに対して4,100円かかります。
MAZDA2を例に挙げると以下のとおりです。
MAZDA2の車両重量(1.09トン)は1.5トン以下に該当し、0.5トンあたり4,100円で計算されます。年間12,300円、5年間で計6万1,500円の自動車重量税が発生します。
- 結論
ガソリン車(車両重量1トン~1.5トンの車の場合)は、2回目の車検までの5年間に自動車重量税が6万1,500円かかります。EVはエコカー減税で0円。差額は6万1,500円です。
EVの車検費用についてはこちら
電気自動車(EV)の車検はガソリン車と同じ?検査内容や費用の違いを解説

自動車保険(任意保険)
自動車保険(任意保険)は、自賠責保険(強制保険)で補いきれない賠償に備えるための保険です。保険料は加入者の年齢や車の登録年月日、等級などによって異なります。
EV
一部の保険会社では、EV専用の「エコカー割引」などが適用され、ダイレクト系3社の実例:1,000〜1,600円/年(車両保険なし・指定条件)程度の保険料が軽減されるケースもあります。
ガソリン車
例として、以下の条件で自動車保険に新規加入した場合、年間保険料は2万5,220円となります(車両保険なし)。
———————————-
加入者年齢:31歳
運転者:30歳以上限定
車種:MAZDA2
その他特約:ゴールド免許
———————————-
- 結論
「EV割引」が年間1,500円の割引が受けられた場合、8年間で保険料がガソリン車より1万2,000円抑えられます。
車検費用
車検はEVもガソリン車と同様に受ける必要があります。車検のタイミングも同じで、新車登録から3年後、以降2年ごとです。
車検費用は依頼先によって異なります。
EV
EVの車検は、ガソリン車とほぼ同じ内容で実施されます。ただし、EVにはエンジンがないため、排気ガス検査やオイル漏れ検査といった項目はありません。その分、検査項目が一部簡略化される点が特徴です。
車検時にはタイヤの摩耗状況もチェックされますが、EVは車体が重く加速性能も高いため、タイヤの摩耗が進みやすい特性があります。そのため、摩耗に強いEV特有のロードノイズを軽減する設計の「EV専用タイヤ」の使用が推奨されています。
なお、EV専用タイヤはサイズや性能にもよりますが、一般的なガソリン車用タイヤに比べて数千円〜数万円高い傾向です。
※走行パターン次第でタイヤ摩耗=想定外コストになり得るため要留意
一方で、EVはエコカー減税の対象となっているため、自動車重量税が初回と2回目の車検時には免除されるなど、税制面での優遇措置もあります。これにより、トータルの車検費用はやや抑えられるでしょう。
ガソリン車
ガソリン車では、EVの車検内容に加えて検査項目があります。排ガス検査やマフラーの騒音測定、エンジンオイルの漏れチェックなどは、エンジンを搭載する車両ならではの確認事項です。
また、ガソリン車ではエンジンオイルやオイルフィルター(エレメント)の交換が定期的に必要で、これも車検費用の一部として計上されます。
- 結論
EVとガソリン車の車検費用は、車両の経過年数や走行距離などによって個別に異なりますが、基本的な検査内容は共通です。外装・内装の点検や、ブレーキ、ライト、ワイパーといった消耗部品の検査は、EV・ガソリン車ともに同様に行われます。
基本的な検査費用は共通していても、タイヤやオイルなど、車両の特性に応じて交換部品は異なります。整備の内容によって、実際の費用には差が出る場合があることを理解しておくとよいでしょう。
バッテリー交換費用
車両は車検だけでなく、日常的なメンテナンスも重要です。なかでもバッテリーは、使用状況に合わせて交換が必要になります。ここでは、その交換費用について解説します。
EV
EVには「駆動用バッテリー」と「補機用バッテリー」という2種類のバッテリーが搭載されています。
駆動用バッテリーは、モーターを動かし車を走らせるためのものです。一方、補機用バッテリーは、ライトやオーディオ、カーナビなどの電装品を動かすために使用されます。
どちらも消耗品であり、経年劣化や使用状況に応じて交換が必要です。
駆動用バッテリーの交換費用は高額で、車種によっては40万円台後半〜100万円超かかることもあります。劣化の進行状況によっても交換時期や費用は変動します。メーカーによっては「8年または16万km」程度を交換の目安としていますが、使用環境によって劣化具合が異なるためこれには限りません。
一方、補機用バッテリーは一般的に3〜10万円程度の費用で交換が可能です。価格は車種やバッテリーの容量によって異なります。
ガソリン車
ガソリン車には、EVのような駆動用バッテリーは搭載されていないため交換は不要です。ただし、エンジン本体を積み替える場合には数十万円〜100万円程度の費用がかかることがあります。
ガソリン車にもエンジンの始動やライト、オーディオなどの電装品を動かすためのバッテリーがあり、劣化状況に合わせて交換が必要です。バッテリーの寿命は2~3年程度とされています。寿命が近づくと、エンジンのかかりが悪くなったり、ヘッドライトが暗くなったりするなどの症状が現れます。
交換費用は車種やバッテリーの容量によって異なりますが、数千円〜5万円程度が一般的です。近年では車両の大型化やバッテリー材料の価格上昇により、交換費用がやや高くなる傾向も見られます。
- 結論
EVとガソリン車、いずれもパワートレインの交換となれば、高額な費用が必要です。
また、バッテリーについてもEVの方が価格帯が高めであることが多く、トータルの交換コストは、EVの方がやや高い傾向にあります。EVもガソリン車も、バッテリーの状態を日頃から把握し、計画的にメンテナンスすることが重要です。
EVは長期保有でコスト優位—ただし初期投資とバッテリー寿命に注意
EVは車両購入費用とバッテリー交換費用が高額ですが、それ以外では税制上の優遇もあってコストを抑えられることがわかりました。
ネックとなる車両購入費用も、補助金を活用することで大幅に下げられます。EVの購入を検討している人は、補助金が交付されているうちに購入するのがおすすめです。
まとめ
EVは車両が高額ですが、ランニングコストはお得といえるでしょう。今後は、充電ステーションなどEVを取り巻くインフラも充実し、ますます使いやすくなる傾向です。コストや環境への配慮、さまざまな面でメリットがあるEVをライフスタイルに合わせて取り入れてみてはいかがでしょうか?