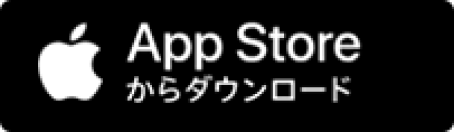INDEX
「電気自動車(以下、EV)の航続距離は短いって聞いたけれど本当?」「遠出するのにEVは向いてないの?」と疑問を抱いている方は多いでしょう。EVはガソリン車に比べて航続距離が短い傾向です。しかし技術が進歩し、ガソリン車と同様に500km以上走れる車種もあるため、一概に航続距離が短いとは言えません。
この記事では、EVの航続距離について解説します。気になる電欠対策や航続距離を延ばす秘訣についても紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
EVの航続距離は?
航続距離とは、EVが満充電の状態で走行できる最大距離です。ここでは、EVの航続距離について知っておきたい基本を紹介します。
航続距離の定義と目安
一般的にEVの航続距離は、車種やバッテリー容量によって異なります。軽EVである日産サクラの航続距離は180km、普通車クラスである日産リーフの航続距離は400kmです。また、上位モデルでは600km以上の航続距離も実現しています。
EVの購入をする際には、用途やライフスタイルに合わせて適切な航続距離を選ぶことが重要です。日常使いが中心の場合は200km程度の航続距離でも十分ですが、長距離の移動や旅行が多い場合は、400km以上の航続距離を備えた車種を選ぶと、充電回数が減り安心して利用できます。
ガソリン車との違い
EVとガソリン車は、航続距離に大きな違いがあります。ガソリン車は、ガソリン満タンから給油が必要になるまでに400km以上走れる設計が一般的です。
EVとガソリン車の航続距離を比較してみましょう。
| 日産サクラ | 日産デイズ | |
| 燃料 | 電気 | ガソリン |
| 航続距離 | 180km | 567km (燃費21.0 km/L【WLTCモード】、燃料タンク27L) |
※実際の走行距離は利用状況によって変動する
EVのサクラは、同じサイズのデイズと比較すると航続距離が短いとわかります。ガソリン車のほうが長い距離を走れる場合がほとんどです。
しかし、サクラの航続距離である180kmとは、東京から静岡の直線距離です。遠出をする場合も、休憩時に1度急速充電を行えば問題ないでしょう。
航続距離の実際はカタログ値より少ない
実際の航続距離や電費は、ガソリンの燃費と同様にカタログに記載されている数値通りにはいきません。なぜなら、実際の走行では、気温や道の状態の影響を受けるためです。
実際の航続距離は、カタログ値の約7割を目安として考えましょう。
EVの航続距離別使用方法
EVは、航続距離が軽自動車クラスと普通車クラスで異なるため、使用方法に応じて選びましょう。車を普段どのように使っているかを確認すれば、自分に必要なスペックが理解できます。
日常的に街乗りするなら軽自動車で十分
街乗りに使用する方なら、航続距離が200km程度の軽自動車クラスを選ぶと使い勝手が良いでしょう。一般社団法人日本自動車工業会の2023年の統計によれば、一日あたりの走行距離の平均は19km、月間走行距離の平均は362kmとなっています。(参照:JAMA2023年度 乗用車市場動向調査)
そのため、通勤や通学または日々の買い物に利用する方は、軽自動車で十分使い勝手が良いでしょう。EVに乗っていない時間帯に、自宅で充電できれば手間も少なく便利です。
遠出をするなら普通車に注目
走行距離が長い方は、航続距離400km以上のEVだと安心できるでしょう。例えば、東京都から大阪府までの距離は500kmほどです。
航続距離が200kmのEVに乗っていた場合、充電の回数が多くなるため、移動にかかる時間が長くなってしまいます。単身赴任中で毎週自宅に帰っていたり、仕事で長い距離を行き来する必要があったりする場合は、航続距離が長い車種を検討しましょう。

EVの航続距離に影響する要因
EVの航続距離は、バッテリーや車両の重量などさまざまな影響を受けます。ここでは、どのような影響を受けるのかを見ていきましょう。
バッテリーの容量と性能
EVはバッテリーの容量が大きいほうが航続距離が長くなります。たくさんの電気をバッテリーに入れられるためです。
また、バッテリーの容量が大きくても劣化すると充電した電気がすぐになくなってしまいます。EVに使われるリチウムイオン電池は、スマートフォンに使用されるバッテリーと同じもので、繰り返し充電していると、だんだん充電の持ちが悪くなります。
車両設計
効率よく設計されたEVは、より航続距離が長くなります。具体的には、アルミやマグネシウムなどの軽量素材を使って車両全体の重量を減らすことで、EVを動かすための力が少なく済むため、航続距離を延ばせる仕組みです。
さらに、部品点数や構造の簡素化も航続距離の向上につながります。EVの駆動用モーター、インバーター、ギヤを一体化したユニットであるeアクスルは、その典型例です。eアクスルについては、以下の記事で詳しく解説しています。
内部リンク:eアクスルとは?EVシフトを進める駆動ユニットの重要性を解説
用語集:eアクスル
運転スタイルと気候条件
運転のスタイルや気候条件によっても、電気の減り方が変わり、航続距離に違いが出ます。例えば、エアコンを使う場合です。エアコンを使うと電気を消費するため、走行するための電気エネルギーが減ってしまい、航続距離は短くなります。
特に、暖房はガソリン車と構造が異なるため消費電力が多いです。ガソリン車はエンジンが発する熱を暖房に利用しています。EVのモーターはあまり発熱しないため、電気で熱を作り出す必要があるためです。
【車種別】最新EV航続距離ランキングとスペック比較表
EVの航続距離は、一般的にどのくらいなのでしょうか。ここでは、国内で販売されている最新EVの航続距離をランキング形式で紹介します。なお、航続距離は最高グレードを記載しています。
| 車種 | 航続距離(WLTCモード) |
| 日産サクラ | 180km |
| 日産リーフe+ | 450km |
| 日産アリア | 640km |
| ヒョンデIONIQ 5 | 703km |
| テスラモデル3 | 706km |
※2025年8月時点
一般的には大型車種のほうが、より容量の大きいバッテリーを積載できるため航続距離が長い傾向です。
EVの航続距離を延ばす運転テクニック
EVの魅力を最大限に生かすためには、日常の運転テクニックが重要です。航続距離を少しでも延ばす工夫をすることで、充電の手間を減らし、より快適なカーライフを実現します。ここでは、すぐに実践できる具体的なテクニックを紹介します。
エコドライブを心がける
EVの航続距離を延ばす最も効果的な方法の一つが、エコドライブです。急な加速や減速を控え、アクセルはやさしく、一定の速度を保つよう心掛けましょう。
特に、発進時は穏やかにアクセルを踏むことがポイントです。急発進・急ブレーキは電力消費を増やす原因になります。アクセルを踏みっぱなしにせず、下り坂などではアクセルを外して回生ブレーキを活用すると、効率よくバッテリーを使えます。
また、多くのEVに搭載されている「エコモード」を利用すると、モーター出力や空調が最適化され、無駄な電力消費を抑えられるためおすすめです。
不要な荷物を積まない
車内に不要な荷物を置いたままにしておくと、航続距離を短くする原因になります。というのも、不要な荷物の分、車両重量が増え、発進や加速時に余計なエネルギーを消費してしまうためです。
EVは重量の影響を受けやすいため、定期的に車内を整理し、使わない道具や荷物を下ろしておくことが、航続距離を延ばすポイントといえるでしょう。
暖房の使いすぎに注意
EVはガソリン車と比較すると、暖房の利用に多くの電力を消費します。車内を暖める際は、エアコンの暖房を必要最小限にとどめ、シートヒーターやステアリングヒーターを併用すると効果的です。
冬場は外気温の低下でバッテリー効率が下がるため、暖房を控えめにし、走行前に自宅で充電しながら事前に車内を暖めておくのもよいでしょう。
タイヤの空気圧を適切にする
タイヤの空気圧が低いと路面との抵抗が増え、電力をより消費します。そのため、適正な空気圧を保つことで走行抵抗が減少し、電費が向上し航続距離の延長につながります。月に一度はタイヤを点検し、メーカー指定の空気圧を維持しましょう。
EVの電欠が不安な場合の対策2選
EVの航続距離がガソリン車よりも短いことから、不安を感じるのはEVのガス欠である電欠でしょう。しかし、事前に電欠の対策を立てておけば心配する必要はありません。ここでは電欠の対策方法を2つ紹介します。
計画を十分に立ててドライブする
電欠にならないためには、計画を立ててドライブしましょう。例えば、ロングドライブをする場合は、充電ステーションをあらかじめチェックしてルートの計画を立てておくと電欠を防げます。
事前に複数個所の充電ステーションを把握しておき、走行中は近場の充電ステーションをチェックしておくとより安心してドライブを楽しめるでしょう。
電欠時に頼れるロードサービスをチェックしておく
万が一電欠になった時のために、頼れるロードサービスを確認しておくのも一つの方法です。JAFや加入している自動車保険についているサービスを把握しておきましょう。
実際に事故や電欠した場合の連絡先をスマ―トフォンにメモしておいたり、ダッシュボードにメモを入れておいたりすると、いざというときに焦らず対応できます。電欠になった際の対処方法を詳しく知りたい方は、以下の記事がおすすめです。
内部リンク:電気自動車(EV)の電欠とは?予防策と対処法を徹底解説

EVの航続距離を向上させる技術
EVの航続距離を向上させる技術として、自動車メーカーや電機メーカーなどさまざまな企業が切磋琢磨しています。ここでは、新世代のバッテリー技術についてやエネルギー回生システムなどを紹介します。
新世代バッテリー技術の革新
EVの航続距離を延ばすために、新世代のバッテリー技術として全固体電池の開発が進んでいます。全固体電池は、従来のリチウムイオン電池に替わる次世代の蓄電技術です。電解質に液体ではなく固体材料を採用することで、エネルギー密度が高く、より多くの電力を蓄えられます。
全固体電池は、航続距離を伸ばすだけでなく、発火や漏液のリスクを大幅に低減する点もメリットです。一部企業は2025年ごろの量産を目指していると発表していますが、本格的な普及にはまだ時間がかかると見られます。
エネルギー回生システムの進化
エネルギーを電気として蓄える回生システムも進化しています。EVではモーターを発電機として電気に変えることが可能です。モーターを制御するインバーターがついていると、下り坂を走った際に電池残量が増えます。
このシステムは、Audiから販売されているe-tronでも活用され、日常のさまざまなシーンで回収したエネルギーを走行中に充電しています。よりエネルギーをうまく回収するシステムが進化すれば、走行距離の向上につながるでしょう。
車体設計と空力特性の改善
車体の設計や空力特性の改善にも各メーカーが力を入れています。使用する電力を減らすため、車両を軽くする方法です。例えば、鉄鋼のように重たい部品からアルミ合金のように軽い部品へ変更が進んでいます。
また、空力抵抗を抑え、空力性能を向上させるための技術開発も進行中です。韓国の現代自動車と起亜自動車では、フロントバンパーと前輪の間に空気が流れる「アクティブ・エア・スカート(AAS)」技術を採用した装置を設置し、バンパー下部から入る空気の流れと、タイヤ周辺で発生する乱流を効率的に制御することに成功しました。
EVの航続距離を見極めるポイント
EVの航続距離がガソリン車と比較して短いことから、不安を感じる方もいるでしょう。しかし、実際には航続距離は十分な場合がほとんどです。ここでは、ご自身のライフスタイルに航続距離が足りるのか、セルフチェックする方法を解説します。
1.パターン別に普段の走行距離を把握する
まずは「1回の移動でどれだけ走行するか」「週や月の合計移動距離はどれくらいか」を日常生活で記録します。記録することで、通勤、買い物、休日の外出、それぞれの最大距離が把握できるでしょう。
次に、何日ごとに充電が必要か、利用頻度の高いルートに充電ステーションがあるのかを確認します。もし長距離移動が月に数回のみなら、その日だけ対策を立てれば、問題なくEVを使用できるでしょう。
2.カタログ値ではなく「実用航続距離」を把握しておく
EVのカタログに書かれている航続距離は、実数値ではありません。そのため、カタログ値の7割の距離を目安として計算しておくと安心です。
例えば、日産リーフの場合の航続距離の実数値は、以下の通りです。
(カタログ値)400km×0.7=(実数値)280km
週末の旅行や出張などで280kmを超える距離を連続して走る方や、1週間あたりの合計走行距離が280kmを大きく超える方は、途中で充電が必要になります。その場合は、より航続距離の長いEVを検討したほうがよいとわかります。
3.充電ステーションの場所を事前に調べておく
自宅に充電設備を設置できるかどうかや、職場、生活圏内に充電ステーションがあるかどうかは、必ず事前に確認しておきましょう。充電設備が身近に整っていれば、航続距離が短くてもEVの使用に支障はありません。
特に自宅に充電設備を設置できると、おうち時間に充電ができEVの利便性が上がります。自宅に設置する際にかかる費用については、こちらの記事をご覧ください。
内部リンク:EV充電設備を自宅に設置するには?気になる費用や注意点を解説
マンションのような集合住宅に住んでいて自宅に充電設備を設置できない場合はこちらの記事をチェックしてください。
内部リンク:マンションにEV充電器がなくても大丈夫!充電問題を解決する方法を解説
【体験したい方向け】レンタカーやカーシェアでEVを試す
実際に体験をしないとEVの航続距離に関しての不安がぬぐえない方は、レンタカーやカーシェアの利用がおすすめです。EVを数日使ってみることで、自分の利用パターンに対する航続距離の「不安」や「不都合」がないか、実体験で確かめられます。
この方法で、「電池残量管理の感覚」や「充電のタイミング」も体感可能です。レンタカーについては以下の記事で解説しているため、ぜひご確認ください。
内部リンク:電気自動車(EV)をレンタカーで体感してみよう|気になる料金も解説
EVの航続距離に関するよくある質問
ここではEVの航続距離に関して、よくある質問に回答しました。疑問のない状態でEVの購入を検討しましょう。
バッテリーを劣化させる要因を教えてください
バッテリーの劣化する速度は、充電の頻度や走行距離、運転の仕方などさまざまな理由によって異なります。バッテリーの劣化につながる主な要因は、頻繁に完全放電してしまったり急速充電を繰り返し行ったりすることです。
さらに急発進や急加速、長時間の高速走行はバッテリーが高温になりやすいため、劣化のスピードが加速します。バッテリーの寿命は、適切な使用方法と定期的なメンテナンスで延ばせるため、日頃から意識しておくことが大切です。
航続距離を延ばす方法はありますか
バッテリーに負荷をかけない運転方法は、航続距離を延ばせます。例えば、エコドライブを心がける、荷物を積みすぎない、タイヤの空気圧を適切に保つなどの方法です。また、エアコンの使いすぎを控えることも効果的です。
このような工夫を日常的に意識することで、航続距離の向上だけでなく、バッテリーの寿命延長にもつながります。
国産EVのなかで航続距離が長い車種が知りたい
2025年7月現在、国産EVのなかでは、日産アリアやリーフe+などが航続距離の長い車種として挙げられます。日産アリアの航続距離は、約470~610km(WLTCモード)、日産リーフe+は約450km(WLTCモード)です。
航続距離を延ばすための技術開発が進んでいるため、今後も続々と航続距離の長い車種が増えていくことが期待されます。
航続距離が長い車種にデメリットはありますか
航続距離が長いEVは、車両価格が高いというデメリットがあります。航続距離を長くするための大容量バッテリーを製造するコストがかかるためです。
さらに、車両重量の増加による運動性能や小回り性能の低下、大型化による取り回し難化などのデメリットもあります。また、一般的にバッテリーが大きいほど充電時間も長い傾向です。
航続距離が短いEVのメリットは何ですか?
航続距離の短いEVのメリットは、車両価格がリーズナブルなことや小回りが利くことです。航続距離の短いEVには、軽EVが挙げられます。
日産サクラやホンダN-VAN:eなどの軽EVの車両価格はコンパクトEVやセダンEVよりもリーズナブルです。軽EVはコンパクトなため渋滞時や狭い道でも運転がしやすいメリットがあります。
軽EVについて詳しく知りたい方は、以下の記事がおすすめです。
内部リンク:軽EVの価格を徹底分析!おすすめ車種やメリットやデメリットも解説
EVを利用するなら「Myプラゴ」をチェックしよう
この記事では、EVの航続距離について紹介しました。EVの航続距離はガソリン車に劣らない車種もあります。使い方に応じて、航続距離が200km程度の車種か400km以上の車種かを選びましょう。
EVを利用するなら、プラゴによる充電認証サービス「Myプラゴ」がおすすめです。Myプラゴはスマホアプリで、充電ステーションを検索しそのまま予約ができる優れものです。決済までスマホで完結できるため、充電後にすぐ出発できます。気になる方はぜひ検討してください。