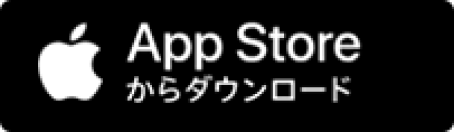NEWS
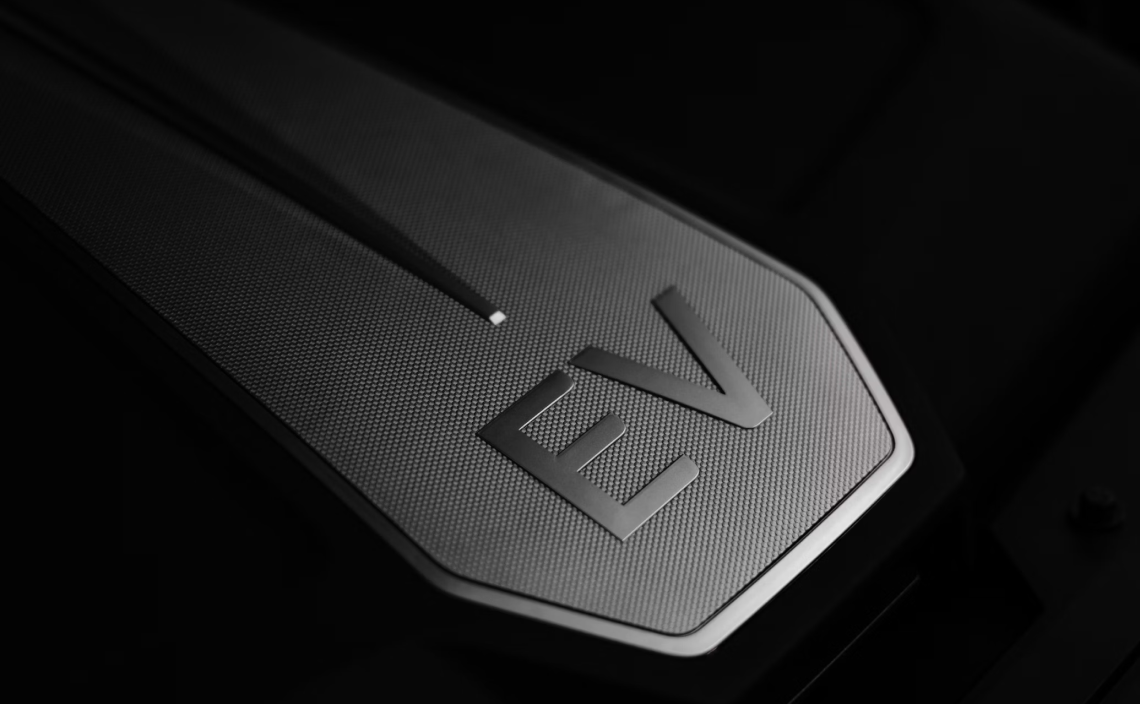
電気自動車(以下、EV)の効率性を支える重要な技術、回生ブレーキは、減速時に発生する運動エネルギーを電力に変換し、再利用する仕組みです。この仕組みは、EVの性能向上に欠かせない重要な役割をもっています。
この記事では、EVの立役者ともいえる回生ブレーキの仕組みを詳しく解説します。また、回生ブレーキを効果的に活用する方法や、航続距離を延ばすためのコツも紹介していますので、EVの性能向上に興味がある方はぜひご一読ください。
回生ブレーキとは?
車を減速させるためにブレーキペダルを踏むと、エネルギーが発生します。回生ブレーキではこのエネルギーを無駄にせず回収し、電力に変換してバッテリーに蓄えることが可能です。ここでは、回生ブレーキの仕組みをさらに解説します。
EV用語辞典:回生ブレーキ
回生ブレーキの仕組み
ガソリン車のブレーキは、減速時にドラムやディスクで摩擦を生じさせて車を止めますが、回生ブレーキは主に摩擦を使わず、モーターによる発電で減速する仕組みです。エンジンブレーキに似た感覚で速度を調整するのが特徴です。
回生ブレーキでは、アクセルペダルを戻すと車輪の回転エネルギーがモーターに伝わり、モーターが発電機として機能します。この過程で得られたエネルギーは、リチウムイオンバッテリーに蓄えられ、後に走行用の電力として利用される仕組みです。
従来のブレーキで消費されていたエネルギーを回収できるため、EVの効率的な走行が実現し、航続距離が延びます。そのため電力を活用し、エコでスマートな走行を可能にするシステムといえるでしょう。
回生ブレーキが搭載されているEV
回生ブレーキは、バッテリーEV(BEV)、プラグインハイブリッド車(以下、PHEV)、ハイブリッド車(以下、HEV)など、多くのEVに搭載されています。EVの車種によっては、回生ブレーキの強さをカスタマイズできる機能があり、走行環境や運転者の好みに応じて制動感を自在にコントロールすることが可能です。
例えば、三菱アウトランダーPHEVやヒョンデIONIQ5、メルセデス・ベンツEQAなどの車種では、ハンドルのパドルシフトを使って回生ブレーキの強弱を変更できます。回生ブレーキは、エネルギーの効率的な回収だけでなく、運転の快適さや楽しさをも向上させる機能ともいえるでしょう。

回生ブレーキのメリット3選
EV独自の技術として、エネルギー効率の向上に貢献する回生ブレーキ。以下では、回生ブレーキで得られるメリットを3つ紹介します。
航続距離が延びる
第一のメリットは、航続距離が長くなることです。ガソリン車の場合、減速時に発生するエネルギーはブレーキの摩擦によってそのまま消費されます。しかし、EVでは回生ブレーキによって減速時のエネルギーを回収し、それをバッテリーに再充電することが可能です。
特に、信号が多い市街地や坂道が頻繁にある場所では、減速する機会が増えるため、その分だけ効率よくエネルギーを回収できます。これにより、実質的に航続距離が延び、充電の頻度も減少します。結果として長距離ドライブや日々の通勤などでも、より快適に安心してEVを利用できるようになるでしょう。
ブレーキパッドが長持ちする
回生ブレーキの大きな利点は、摩擦がほとんど起こらないため、ブレーキパッドの寿命が長くなることです。従来のブレーキシステムでは、ドラムやディスクを使って摩擦で減速させるため、ブレーキパッドが頻繁に摩耗し、定期的な交換が必要です。
しかし、回生ブレーキでは、減速時にモーターが発電を行い、そのエネルギーを電気に変換することで車両の速度を落とします。このプロセスでは、摩擦がほとんど発生しないため、ブレーキパッドの負担を抑えられます。その結果、ブレーキパッドの交換頻度が少なくなり、メンテナンスコストの削減が可能です。長期的には、ランニングコストの低減にもつながります。
環境負荷の低減
環境への配慮が求められる今、回生ブレーキはそのカギを握る技術のひとつです。CO2排出量の削減は重要なテーマであり、回生ブレーキは減速時の運動エネルギーを無駄なく電力へと変換することで、電費向上に貢献します。
特にHEVやPHEVなど、エンジンとの併用が前提の車両では、回生ブレーキの活用によってエンジン稼働や摩擦ブレーキの使用頻度が抑えられるため、効率的なエネルギー運用が可能です。
つまり回生ブレーキは、走るたびに省エネにつながる、未来志向のクリーンテクノロジーといえるでしょう。
回生ブレーキのデメリット
回生ブレーキは、すべてにおいて万能というわけではありません。以下では、回生ブレーキのデメリットを見ていきましょう。
パーツが多くなり車両が重くなる
回生ブレーキを搭載することで、車両のシステム構成がより複雑になるという側面があります。従来の摩擦ブレーキに加えて、モーター機能を持つジェネレーターやインバーター、さらに回生ブレーキで回収したエネルギーを蓄えるバッテリーなど、専用の電動部品が新たに必要になるためです。その結果、電子制御系のコンポーネントも増加し、車両全体の構造はより緻密になります。
これらのパーツが加わることで車両重量が増し、電費や燃費の効率に少なからず影響を与えるでしょう。加えて、車両重量の増加に伴ってタイヤの摩耗が早まり、長期的なメンテナンスコストへの影響も考えられます。
ただ、EVはもともと電費効率に優れた設計が施されており、多くのユーザーにとってはこれらのデメリットは実用上、あまり気にならないレベルに留まるケースが多いのも事実です。
低速域での発電効率改善が課題
回生ブレーキの発電効率を低速域でも維持することは、いまなお解決が求められる技術的ハードルのひとつです。特に、徐行や停車間際のタイミングではモーターによる発電効率が著しく下がり「回生失効」と呼ばれる状態に陥ることがあります。
この現象により、十分なエネルギー回収ができず、補助的に摩擦ブレーキを使わざるを得ない場面もあるため注意が必要です。せっかくの回生ブレーキの利点が発揮されにくくなってしまいます。
EVやPHEVといったエネルギー再利用を重視する車両にとって、低速域の発電効率向上は、解決が急がれる課題です。現在では先進的な蓄電装置を活用し、効率よく余剰電力を蓄える技術の研究・実用化が進められています。
回生ブレーキを効率よく使うコツ
運転の工夫により、さらに回生ブレーキの効率は高まります。ここでは、電力回収量を高め、より効率よく走行するためのコツをまとめました。
急発進や急加速を避ける
回生ブレーキの効果を最大限に活かすには、急発進や急加速を避けることが重要なポイントです。
回生ブレーキはあくまで緩やかな減速時に力を発揮する仕組みのため、急激なスピードの変化には十分なエネルギー回収が追いつかないことがあります。さらに、バッテリーが満充電の状態ではそれ以上の電力を受け入れられず、場合によっては、せっかく発電しても回収が行われません。
一方、急ブレーキのような強い制動をかけると「回生協調制御」が作動して、摩擦ブレーキも併用され、回生によるエネルギー回収量が減ってしまいます。そのため、できるだけ緩やかな減速を心がけることが大切です。
早めにアクセルを戻して自然な減速を
回生ブレーキの性能を最大限に引き出すコツは、アクセルペダルを早めに離して減速を始めることです。早めの減速をすると、回生ブレーキが無理なく作動し、効率よくエネルギーを回収できます。
また、信号や交差点の位置を先読みすれば、早めに減速を始められ、余剰エネルギーをしっかり回収できます。スムーズな予測運転は、エネルギー効率のカギを握るでしょう。
どうなる?回生ブレーキの未来
回生ブレーキは、効率性や性能の進化が期待される技術です。未来の回生ブレーキはどんなものになるのか、注目されるポイントを紹介します。
回生ブレーキの市場は2029年までに大幅に拡大
回生ブレーキ市場は、2022年の約60億米ドル(約7,800億円)から、2029年には119億8,000万米ドル(約1兆5,574億円)へと、ほぼ倍増する勢いで拡大すると見込まれています。その背景には、EVへの移行の加速に加え、燃費向上や排ガス削減といった環境対応へのニーズの高まりがあるからです。
今後は商用EVへの導入も本格化し、配送車両やバスといった業務用車両においても回生ブレーキの活用が広がると期待されています。これにより、自動車業界全体での技術需要はさらに増し、回生ブレーキ市場はますます存在感を強めていくことでしょう。
アクセルだけで操作するワンペダルドライブで操作が楽に
近い将来、EVの運転はますますスマートになるでしょう。ワンペダルドライブによってアクセル操作だけで加減速が可能になると考えられています。
ワンペダルドライブとは、アクセルを踏めば加速し、緩めれば減速できる技術です。ブレーキとアクセルの踏み間違いを防ぐことができ、安全性の向上にもつながります。さらに、アクセル操作だけで走行をコントロールできるため、エネルギー効率にも優れ、効率的な電力回収が可能です。
ワンペダルドライブはまさに、回生ブレーキの働きを活用できる技術です。今後、回生ブレーキがさらに進化すれば、運転の快適性も格段に向上するでしょう。
EV用語辞典:ワンペダルドライブ
まとめ
エネルギーの再利用技術として注目される回生ブレーキは、年々進化を遂げています。無駄を出さず効率よくエネルギーを活かすこの技術は、環境負荷の低減にも大きな役割を果たす存在です。今後はさらに、持続可能な社会の実現に向けた強力な支えとなるでしょう。回生ブレーキは、未来の移動手段をよりサステナブルで心地よいものへと導くと期待されています。