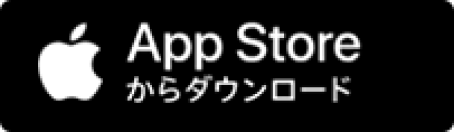電力の瞬間的な大きさを表すkW(キロワット)と、消費した電力の量を表すkWh(キロワットアワー)。これらの違いを正しく理解していますか?2つの単位は、電気自動車(以下、EV)に関連してよく登場します。しかし、実際にこれらが何を意味しているのか、はっきりと説明できる方は少ないのではないでしょうか?
この記事ではkWとkWhの意味と、それぞれがどのように計算され、どんな場面で役立つのかを説明します。これを読めば、EVの充電時間や電費の感覚もつかみやすくなるでしょう。すでにEVに乗っている方はもちろん、これからEVをお考えの方もぜひ参考にしてください。
kWとkWhの基本概念
kWとkWhは、電力とエネルギーの単位です。ここでは、kWとkWhそれぞれの定義と違いをまとめました。
kWとは?
kWは、瞬間的な電力の大きさを示す単位で、1秒間あたりの電気の仕事量を表します。1,000Wは1kWとも表され、ドライヤーで「1,200W」と表示されているものは「1.2kW」と同じです。
例えば、600W(ワット)のドライヤーと1,200Wのドライヤーを比較すると、同じ時間であれば、1,200Wの方がよりパワーがあります。
Wが大文字で表記されるのは、この単位がスコットランドの発明家ジェームズ・ワットに由来する人名単位であるためです。
kWhとは?
kWhは、消費される電力量を示す単位です。例えば電化製品を作動させるために必要な電気の量を表します。
kWhの「h」は、時間(hour:アワー)を意味し、1kWの電力を1時間使用すると1kWhになります。1.2kW(1,200W)のドライヤーを1時間使った場合、消費電力は1.2kWhです。
このように、kWhは電力消費の累計を表し、電気代は一般的にkWhをもとに計算されています。
kWとkWhの違い
kWとkWhは、電力と電力量をそれぞれ表す単位です。kWは瞬間的なエネルギーの大きさを示し、蛇口から出る水の流れに例えられます。
一方、kWhはその流れた水がたまった量と考えられ、実際に使用した電気すべての量です。これを電気の「使用量」として考えると、1kWのドライヤーを1時間使用した場合、そして2kWのドライヤーをその半分の時間、30分使った場合の電気代は同じです。このことからkWは電気の「大きさ」、kWhは電気の「使用量」を示していることがわかるでしょう。

EVに使われる電気の単位
kWとkWhは、EVにおいて切り離せない単位です。EVに関係する電気の単位は、kWとkWh以外にもあります。ここでは、EVに使われている電気の単位をまとめました。
kW(充電器)
EVの充電器における「kW」は、充電器の出力の大きさを示す単位です。普通充電器の出力は、一般的に自宅や公共施設に設置されているもので3~6kW程度です。急速充電器は一般的に50kW〜90kW程度と出力が高く、普通充電と比べて充電時間が短くなります。さらに最近では、150kWを超える「超急速充電器」も登場しており、一部の対応車種では、短時間で大容量の充電が可能です。普通充電と比べて充電時間が短くなります。
例えば、バッテリー容量50kWhのEVを、50kWの急速充電器で30分充電すれば、バッテリーの50%程度を充電することが可能です。
kWh(バッテリー容量)
EVのバッテリー容量は、フル充電の状態で取り出せる電力量としてkWhの単位で表されることが一般的です。この数値が大きいほど、一度の充電で走行できる距離が長くなります。
バッテリー容量は車種によって異なりますが、例えば軽EVの日産サクラは20kWh、普通車EVの日産リーフのバッテリー容量は、40~60kWhです。
一方、PHEV(プラグインハイブリッド車)では、バッテリー容量をAh(アンペアアワー)という単位で表す場合もあります。kWhやAhは、EVのバッテリー容量を把握するための重要な単位ともいえるでしょう。
km/kWh(電費)
EVの電費は、1kWhの電力量で何km走行できるかを示す単位で、km/kWhで表されます。ガソリン車の「1Lあたりの走行距離」を示す燃費と同じイメージです。km/kWhの数値が大きいほど、長い距離を走れる効率の良い車であることを意味します。
例えば、日産サクラの電費は、カタログ値(WLTCモード)で8.06km/kWhです。一方、日産リーフは、40kWhモデルが6.45km/kWh、60kWhモデルが6.21km/kWhとなっています。
なお、一部のメーカーでは、この単位が逆の表記(kWh/km)になる場合もありますが、その場合は数値が小さいほど効率的になります。
V(充電器)
EVの充電器において、V(ボルト)は電圧を表す単位です。充電器の電圧は、電気をどの程度の勢いで供給するかを示し、充電速度に影響を与えます。
家庭用の充電器では交流100Vと200Vの2種類がありますが、EVの充電では200Vを使用することが一般的です。200Vの充電器は100Vに比べて効率よく充電できるため、充電時間を短縮できます。
A(充電器)
EVの充電器では、電流を表すA(アンペア)も重要な指標です。充電器の出力によって必要なアンペア数が変わります。例えば3kW出力の充電器では約15A、6kW出力の充電器では約30Aが必要です。これは、電力(kW)の約5倍のアンペア数を目安とします。
EVの自宅充電時に複数の電化製品を使用するとブレーカーが落ちるため、契約アンペア数の検討がおすすめです。十分なアンペア数を確保することで、安全で安定した充電環境を整えられます。

知っておくと便利!kWとkWhを使った計算式
kWとkWhの基本を理解すると、電気代や電費を把握するのに役立ちます。ここでは、日常で使える計算式を解説します。
充電時間(時間)=バッテリー容量(kWh)÷充電器の出力(kW)
充電時間は、バッテリー容量(kWh)を充電器の出力(kW)で割ることで求められます。例えば、容量30kWhのバッテリーを6kWの充電器を使って充電する場合、計算式は以下のとおりです。
- バッテリー容量(kWh)÷充電出力(kW)=充電にかかる時間(時間)→30kWh ÷ 6kW = 5時間
上記の場合、約5時間で満充電になることがわかります。
しかし、急速充電器ではバッテリーに負担がかからないよう、充電率80%を超えると充電速度が徐々に遅くなります。実際にはこの計算通りにはいかない場合があることをご承知ください。
月間走行距離(km) ÷ 電費(km/kWh) × 1kWhあたりの電気料金(円) = 月の電気料金(円)
自宅でEVを充電する際の電気料金は、月間の走行距離を電費(km/kWh)で割り、そこに1kWhあたりの電気料金を掛けることで求められます。どれだけの電力量を消費し、それにいくらかかるのかを計算します。
例えば、電費が6km/kWh、電気料金が1kWhあたり30円、月間走行距離が100kmの場合、計算式は以下のとおりです。
- 月間走行距離(km) ÷ 電費(km/kWh) × 電気料金(円/kWh)= 1カ月の電気料金(円)→ 100km ÷ 6km/kWh × 30円 = 約500円
上記の場合、毎月の電気料金は500円となります。
詳しい充電料金については、以下の記事をご覧ください。
参考:電気自動車の充電料金完全ガイド:自宅充電から充電ステーションの利用まで徹底解説
電費 航続距離(km)÷バッテリー容量(kWh)
EVの電費は、航続距離(km)をバッテリー容量(kWh)で割ることで求められます。例えば、航続距離180km、バッテリー容量30kWhのEVの場合、計算式は以下のとおりです。
航続距離(km)÷バッテリー容量(kWh)=電費(km/kWh)→180km ÷ 30kWh = 6km/kWh
上記の電費は、6km/kWhです。しかし、電費はブレーキングの加減や外気温、走行環境によっても変動します。特に寒冷地ではバッテリーの効率が低下する傾向です。
また、急発進や加速など、バッテリーに負担をかける走行を避けることで、電費の向上を実現できます。効率的な走行を心がけましょう。
まとめ
kWとkWhはどちらも電気の単位ですが、電気の大きさと総量で意味が異なります。その違いを理解することで、電気料金の計算やEVの充電、さらには日常生活での電力管理がスムーズになります。当記事を通じて、電気の仕組みに対する理解が深まり、より賢いエネルギーの使い方ができれば幸いです。