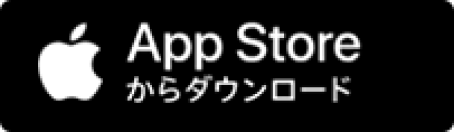INDEX
BEV(Battery Electric Vehicle)はEVとも呼ばれ、ガソリンを使わずバッテリーにためた電気で走行する車です。BEVは、環境性能や静粛性、維持費の安さなど多くのメリットがあります。
将来的に欠かせない存在となることが予想されるBEVですが、充電や航続距離などガソリン車とは異なる使い方が求められます。BEVの特徴を知っておくことでこれらの不安は解消されるでしょう。
当記事では、BEVの基本的な仕組みやガソリン車との違いをまとめました。これからBEVを検討する際に知っておきたいポイントも解説します。未来のカーライフを一緒に探ってみませんか?
BEVはモーターを駆動源とした電気自動車
BEV(Battery Electric Vehicle)は、バッテリーにためた電気をエネルギーとして走行する電気自動車です。ここではBEVの仕組み、ガソリン車との違いを解説します。
BEVの仕組み
BEVは、バッテリーにためた電気を使ってモーターを動かします。「EV」とも呼ばれますが、EVには電気とガソリンの両方で駆動するプラグインハイブリッド(以下、PHEV)を含む場合があるため、区別した名称です。
BEVには、駆動用バッテリーと補機用バッテリーの2種類があります。駆動用バッテリーは、モーターの駆動や空調システム、AC100V給電などに使用され、補機用バッテリーは12V系のシステム稼動や一般電装品の電源供給に用いられます。
ガソリン車との違い
ガソリン車が駆動する流れは以下のとおりです。
- ガソリンと空気を混合してシリンダー内に吸入
- ピストンで圧縮
- 圧縮された混合気を燃焼
- ピストンが上がる時にバルブから排ガスが排出される
ガソリン車は上の一連の流れを瞬時に行う必要があることから、部品の搭載位置が制限されます。
一方、BEVはエンジンがないため、 部品の搭載位置の自由度が高いことが特徴です。
BEVは、減速時にモーターを発電機として利用し、運動エネルギーを電気に変換してバッテリーに回収します。これが「回生ブレーキ」と呼ばれる仕組みです。
通常は油圧ブレーキと協調して作動し、効率よくエネルギーを回収できるよう制御されています。また、モーターの制御技術を活かすことで、滑らかで繊細な減速が可能となり、ガソリン車にはない自然な走行感も実現しています。
用語辞典:回生ブレーキ
BEV以外のモーターで動く車とは?EVの種類
バッテリーだけで駆動するBEV以外にも、モーターを搭載している自動車があります。
HEV(ハイブリッド車)
ハイブリッド(以下、HV)はエンジンとモーターを組み合わせて駆動する車です。BEVやPHEVと違い、HVは車両の外部から充電できません。
HVには3種類あります。
| シリーズ方式 | エンジンを使って発電し、主にモーターで駆動する。 |
| パラレル方式 | 主にエンジンで駆動する。 発進時や加速時など駆動力が必要な場合はモーターを併用する。 |
| スプリット方式 | パラレル方式をさらに細かく制御したもの。 |
上記以外に、小型のモーターとバッテリーでエンジンを補助する「マイルドハイブリッド」もあります。
用語辞典:HEV
PHEV(プラグインハイブリッド車)
PHEVは、HVに外部からの充電機能を追加した車です。バッテリーにたまった電気だけで80kmほど走れる車種もあります。
蓄えられた電気が規定以下になったり、作動モードを変更したりすると、ガソリンで走行することが可能です。ガソリン走行時の燃費も良く、CO2排出量も少ないため、環境に配慮した車といえるでしょう。
用語辞典:PHEV
FCEV(燃料電池車)
燃料電池車(以下、FCEV)は、水素と酸素をエネルギーとして燃料電池自らが発電し、モーターで駆動する車です。水素ステーションで水素を充填します。
燃料電池による電気を一時的に蓄えるバッテリーはありますが、EVと比べて非常に小さく、その代わりに燃料電池と水素タンクを搭載していることが特徴です。水素の充填時間は3分程度で、EVと同等の航続距離で走行できます。
用語辞典:FCEV

BEVのメリット
エンジンを持たないBEVは、環境性能やコスト面で多くの利点があります。ここでは次世代の移動手段として期待されるBEVのメリットをまとめました。
CO2を排出しない
BEVは電気のみで走行するため、ガソリン燃焼時に発生するCO2を排出しません。さらに充電に用いる電力に太陽光、水力など再生可能エネルギーを使えば、走行時にも電気の製造時にもCO2が排出されず、環境負荷を大幅に低減できます。
日本政府は、2021年4月、CO2を含む温室効果ガスを、2030年度には2013年度比で46%削減することを目指すと表明しました(参考:環境省)。CO2を排出しないBEVは、この目標達成にも貢献するでしょう。
静粛性が高い
モーターで走行するBEVは、静かに走行できます。アクセルを踏んだ瞬間に最大トルクを発揮するため、パワフルでありながらガソリン車のようなエンジン内の圧縮、燃焼、排気による音や振動がありません。
一方、走行音が静かになったことで感じられる風切り音やロードノイズも、遮音や吸音などの技術を駆使することで静粛性を上げています。
車内が広い
BEVはバッテリーを床下に設置するため、車内スペースを広く確保できるのが特徴です。ガソリン車(特に後輪駆動車)では、エンジンの動力を駆動輪に伝達するプロペラシャフトがあるため、後部座席付近に段差が生じます。駆動形式が異なるBEVは、後部座席の足元中央がスッキリしています。
維持費を抑えられる
BEVの充電料金は、ガソリン代に比べて安く抑えられることがメリットです。近年ガソリンの高騰が続くなか、BEVはコストを抑えるための選択肢としても注目されています。
EV vs ガソリン車:充電・給油コストの比較で見えるEVの経済性
また、BEVは「エコカー減税」「グリーン化特例」など税の優遇が受けられます。エコカー減税では、購入時と初回の車検時に納入する自動車重量税が全額、グリーン化特例では自動車税の75%が免除されます。
電気自動車の維持費はどのぐらい?補助金からランニングコストまで解説
非常用電源になる
BEVはいわば大容量の蓄電池です。100Vコンセントが搭載されたBEVなら、車内や屋外で電化製品を使用できます。
さらに、BEVに蓄えられた電気を家庭に給電できるV2Hを導入すれば、非常時の電気を数日分賄うことも可能です。
V2Hと電気の自給自足|価格・設置費用を徹底解説!メリットやデメリットも

BEVのデメリット
BEVは多くのメリットを持つ一方、課題も存在します。ここではBEVのデメリットをまとめました。
車両が高額
BEVの車両価格は、性能の高さやバッテリーの生産コストがかかることからガソリン車に比べると高額です。軽EVの日産サクラと軽自動車のルークスでは100万円近くの差があります。
ただし、BEVの購入には国や自治体から補助金が受けられます。補助金額は車種や地域によって異なりますが、国からの補助金(CEV補助金)は最大85万円(軽EVでは55万円)です。自治体によっては、さらに補助金が支給される場合もあります。
EV購入のお金のメリット:最新の税制優遇・補助金情報と賢い活用術
充電に時間がかかる
BEVの充電は、ガソリン車への給油に比べると時間がかかります。充電にかかる時間はBEVのバッテリー容量や電池残量によって異なりますが、バッテリー容量30kWhのBEVを0%からフル充電する場合、普通充電(6kW出力)で約5時間、急速充電(50kW出力)の場合で約40分です。充電時間はバッテリーの状態や充電設備の性能によって変動します。
しかし、自宅や出先でのんびりと過ごす時間や、ドライブの休憩時間を充てることで効率的に充電できます。
以下の記事ではBEVの充電時間をさらに詳しく解説しています。
EV(電気自動車)の充電時間は?効率よく充電するポイントをご紹介
BEVで知っておきたい注意点
BEVの導入や利用には事前に理解しておきたいポイントがあります。ここではBEVについて知っておきたいポイントをまとめました。
充電場所
BEVの充電は、自宅に充電コンセント(普通充電)を設置する以外に、商業施設、カーディーラー、SA・PA(サービスエリア・パーキングエリア)、道の駅、コンビニエンスストアなどに設置されている充電器でも充電可能です。
全国には、2025年3月時点 で普通充電器、急速充電器合わせて約4万口の充電器が整備されており(参照:経済産業省)、自宅に充電設備がなくても不便なく充電できます。
経済産業省は、2030年までにEVの充電設備を30万口まで増やす方針を示しています。今後はさらに充電が便利になるでしょう。
以下の記事ではEV充電器の場所や検索方法などをさらに詳しく解説しています。
EVの充電器はどこにある?|充電ステーションの検索方法やアプリを紹介
航続距離
BEVの航続距離は、バッテリーの容量によって異なります。軽EVでは約200km、普通車クラスのEVでは400km以上走れるモデルも多くなりました。バッテリー容量の増加やエネルギー密度の向上により、航続距離はさらに伸びています。
車が減速する際の運動エネルギーを電気エネルギーとして蓄える回生システムの進化や、電池技術の向上でBEVの航続距離は今後さらに延びるでしょう。
電気自動車の航続距離は一充電でどのぐらい?気になる電欠対策も解説
バッテリーの寿命
メーカーによって違いはあるものの、多くのメーカーではBEVのバッテリー保証期間の目安を8年間または走行距離16万kmとしています。バッテリーを長持ちさせるには、負担のかからない使い方がポイントです。頻繁な充電や急速充電の多用を避けることで、バッテリーの劣化を抑えられます。

軽クラスからSUVまで!トレンドBEVを紹介
BEVの選択肢が広がるなか、軽自動車からSUVまで多彩なモデルが登場しています。ここでは、注目のトレンドBEVをタイプ別に紹介します。購入を検討中の方はぜひ参考にしてください。
以下のスペック情報は、各メーカーの公式サイトに基づき、2025年5月12日時点の内容を掲載しています。
| 車名 | 航続距離 | バッテリー容量 | 価格(税込) | 特徴 |
| 日産:サクラ | 180km (WLTCモード) | 20kWh | 259.93万円~ |
|
| 日産:アリア | 470~640km (WLTCモード) | 66kWh/91kWh | 659.01万円~ |
|
| ホンダ:N VAN e: | 245km (WLTCモード) | 29.6kWh | 269.94万円~ |
|
| BYD:ATTO3 | 470km (WLTCモード) | 58.56kWh | 418万円~ |
|
| ヒョンデ:IONIQ5 | 616~703km (WLTCモード) | 84.0kWh | 523.6万円~ |
|
上記の通り、さまざまな用途のBEVが販売されています。各メーカーは、これからさらにラインナップを充実させる予定です。
BEVはもっと便利で身近な存在に!
BEVは、技術の進化と充電インフラの整備により、ますます便利で身近な存在になりつつあります。ここでは、今後のBEVの進化と期待されるポイントをまとめました。
進化するテクノロジーで安全性と効率性が向上
BEVは、進化するテクノロジーによって、安全性と効率性の両面で大きな進化を遂げようとしています。バッテリー性能の向上により航続距離が伸び、実用性はさらに高まるでしょう。
また、コンパクトカーからSUVまで多様な車種が登場し、選択肢も広がっています。回生ブレーキを活用したワンペダルドライブは、運転中の負担を減らすだけでなく安全性の向上にも貢献できる技術です。
加えて、V2Xが進化することで「車と人」、「車とインフラ」、「車と歩行者」につながりが生まれます。これにより、さらに安心で快適なモビリティ社会が実現していくでしょう。
V2Xについては以下の記事でも解説しています。
V2Xで変わるEVの未来|V2H・V2L・V2Gなど技術をご紹介
拡大するインフラで充電がスピーディーに
EVの充電環境は、今後ますます便利でスピーディーになると期待されています。経済産業省は2030年までに、国内の充電器の設置台数を現在の10倍に増やす方針を発表しました。
加えて、充電器の高出力化も進められ、高速道路では90kW以上、さらに150kW級の超急速充電器の普及も見込まれています。中国と共同開発中のChaoJi規格の実用化が進めば、900kWクラスの充電も可能となり、さらに充電時間が短縮されるでしょう。
また、コネクタを差し込むだけで充電から決済まで完了するプラグアンドチャージ(PnC)の導入も拡大中です。こうしたインフラの進化により、EVの充電はより速く、快適に進化していきます。
充実の補助金で購入しやすく
BEVの購入を検討するうえで、国や自治体からの補助金制度は大きな後押しになります。2025年度は、国から最大85万円の補助が受けられ、車の環境性能に応じて最大5万円が加算される場合もあります。さらに、自治体によっては別途補助金が支給されるケースもあるため、地域の制度も要チェックです。
2025年度の申請期限は以下のとおりです。
| BEVの初度登録 | 申請書提出期限 |
| 2024年12月17日~2025年3月31日 | 2025年5月31日まで |
| 2025年4月1日~30日 | 原則5月31日まで。ただし支払いが未完了の場合は6月30日まで |
| 2025年5月1日以降 | 登録から1カ月以内、支払い未完了の場合は翌々月末まで |
補助金には年度ごとの予算枠があるため、早めの申請が重要です。なお、補助金を受けた車両には3~4年の保有義務期間があり、原則その間の売却はできません。計画的な購入を心がけましょう。
まとめ
BEVは環境に配慮できる点や維持費が抑えられる点、快適な走行性能など、ガソリン車にはない多くの魅力があります。 これから期待が高まるBEVは、単なる移動手段を超えて持続可能な未来を支える存在です。当記事がBEVの理解を深めるきっかけとなり、安全で快適なカーライフに役立てば幸いです。