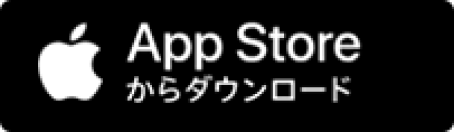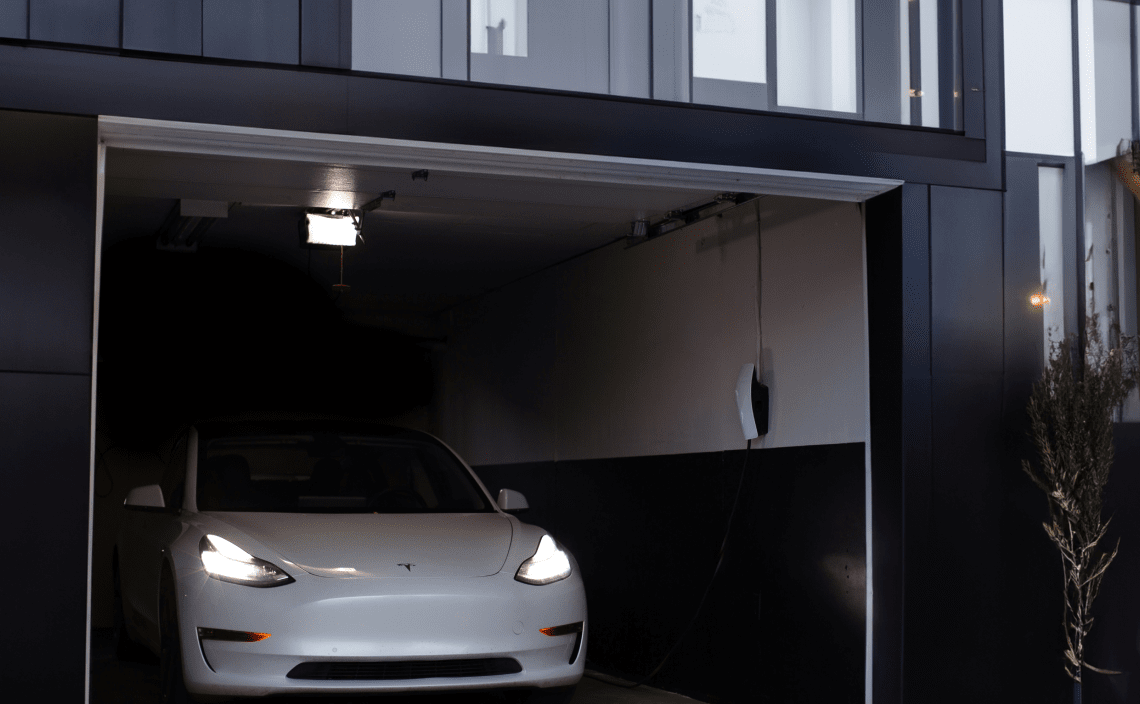
INDEX
V2H(Vehicle to Home)は、電気自動車(以下、EV)を家庭の電力供給源として活用できるシステムです。災害時や停電時に非常用電源として使えるほか、電気料金を節約する効果も期待されます。しかし、その一方で、価格、設置スペース、システムの稼働年数など、懸念点も存在します。
当記事では、V2Hの基本的な仕組みからメリット・デメリット、設置にかかる費用についてまとめました。V2Hを導入するかどうか検討中の方にとっての判断材料になれば幸いです。EVユーザーの方はもちろん、太陽光発電を検討している方も、ぜひご確認ください。
V2Hは導入すべき?EVユーザーが確認しておきたいこと
これから自宅に充電器を設置するEVユーザーの方には、V2Hの導入を視野に入れることをおすすめします。ここではV2Hでできることをまとめました。
V2Hとはどのようなものなのか基本的な部分をおさらいしたい方は、以下のリンクをご確認ください。
内部リンク:V2Hの仕組みとメリットとは?家庭で電気自動車を賢く使う方法を解説
用語集:V2H
V2HはEVと家庭の電気を相互に活用するシステム
V2HはEVに蓄えた電気を家庭に供給することと、家庭の電気をEVに充電することができる仲介システムです。EVの電気を直流から家庭用の交流に変換して給電するため、緊急時や災害時の非常用電源としても活用できます。EVと家庭の電気を相互に活用すれば、効率的な電力管理を実現できるでしょう。
V2Hは、対応モデルに限り、家庭での充電やEVからの給電が可能です。EVの充電といざというときの電力供給を両立するV2Hは、EVユーザーにとって理想的な選択肢といえるでしょう。
V2Hは太陽光発電との連系でさらに威力を発揮
V2Hを太陽光発電システムと連系させれば、太陽光発電によってEVと家庭両方の電気を自給自足できます。たとえば、EVを使わないとき、日中に太陽光発電で作られた電気をEVに蓄え、その電気を家庭で使用するという、電力の流用も可能です。
節電効果はもちろん、数日間にわたって家庭の電力を賄えるため、非常時の備えとしても大きな安心感が得られます。
また、太陽光発電はクリーンエネルギーで、環境負荷の軽減にも貢献できます。日常の充電から非常時の電源、さらには環境保護まで、V2Hを活用することで多くのメリットがあるといえるでしょう。

V2Hのメリット
ここでは、V2Hの導入で得られるメリットについて、より具体的にまとめました。
電気代の節約になる
V2Hを導入すると、電気料金が安い深夜の時間帯にEVへ充電し、昼間にはその蓄えた電力を家庭で使用することができます。これにより、電気代を大幅に節約することが可能です。
実際の導入事例では、月々5,000円~10,000円、年間で最大約10万円ほどの電気代削減が見込まれるケースもあります。節約できる金額は、各家庭の電力消費量やEVのバッテリー容量、電気料金プランなどによって異なりますが、多くの場合で光熱費の大幅な削減が期待できるでしょう。
非常用電源としての役割
V2Hは、災害や停電時にEVやPHEVのバッテリーを家庭用の非常用電源として活用できます。家庭の分電盤と接続し、冷蔵庫や照明、スマートフォンの充電など、生活に必要な家電へ安定した電力の供給が可能です。
EVの大容量バッテリーを蓄電池として利用することで、一般家庭なら数日分の電力をまかなうことが可能です。例えば日産リーフ(62kWh)の場合、使用する家電や消費電力にもよりますが、約2~4日間分の家電や照明を動かせるとされています。いざというときに、電気を使用できる安心感を得られるでしょう。
EV充電の時間短縮
V2Hは、一般的な家庭用普通充電器(出力3kW)と比べて2倍の出力(6kW)を持つため、EVの充電時間を大幅に短縮可能です。EVの充電に普通充電器を使用すると、満充電までに10時間以上かかることがありますが、V2Hを使えば約半分の時間で完了するケースが多く、急な外出や予定変更にも柔軟に対応できます。
これは、V2Hが家庭の交流電力を効率よく直流に変換し、EVへ直接高出力で充電できるためです。忙しい日常や急な外出時でも、短時間で必要な電力量を確保できるのは大きなメリットといえるでしょう。
電力会社からの電気購入量を減らせる
V2Hを活用することで、家庭でのエネルギー利用において電力会社からの電力購入を抑えられ、その結果、温室効果ガスの削減にもつながります。これは、V2HによってEVのバッテリーを家庭用の蓄電池として有効活用できるためです。
特に、電力需要が高まる昼間の時間帯には、多くの電力会社で火力発電所の稼働が増加します。しかし、V2Hを利用すれば、深夜に安価かつ比較的クリーンな電力をEVに蓄え、昼間にその電力を家庭で使う「ピークシフト」が可能です。これにより、昼間の火力発電への依存を下げることができ、持続可能な社会の実現にもつながるでしょう。
補助金が受けられる
V2Hの導入には、自治体や国の補助金を活用できる場合があります。普通充電器よりも、V2Hのほうが設備や工事費が高額なため、補助金を受け取れるのは大きなメリットです。
CEV補助金
2025年のV2H導入に対するCEV補助金は、個人宅・マンションの場合、機器費用に対して1/2(上限50万円)、工事費に対して上限15万円まで支給されます。つまり、合計で最大65万円の補助金を受けることが可能です。(2025年8月公式情報より)
※CEV補助金の情報は、年度や予算状況によって変動があります。なお、CEV補助金が適応される条件にも変動があるため、V2Hを購入する際には事前に公式サイトで最新の制度内容を確認してください。
以下では、CEV補助金について深掘りして解説しています。ぜひご確認ください。
内部リンク:CEV補助金とは?EV購入時に知っておきたいお金の知識
お住まいの自治体からの補助金
CEV補助金に加えて、お住まいの自治体が独自に提供する補助金を併用できる場合もあります。東京都では、機器および工事費の1/2(上限50万円)が補助される制度があります。
自治体ごとの補助金制度を活用することで、V2H導入の費用をさらに抑えることが可能です。お住まいの地域によって補助金制度や金額が異なります。必ず自治体の公式サイトで最新の情報をご確認ください。
内部リンク:EV購入の補助金は東京都でいくらになる?ガソリン車よりもお得?
V2Hのデメリット
メリットが多いV2Hの導入には、いくつかの注意点や課題も存在します。ここでは、V2Hのデメリットを3つまとめました。
価格と設置費用が高額
V2Hの導入には、機器代と設置工事費を合わせて100万円以上の費用がかかる場合があります。この初期費用をデメリットと感じる方もいるかもしれません。しかし、国や多くの自治体がV2H導入を促進するために補助金制度を設けています。補助金を活用することでV2Hの導入費用を大幅に抑えることが可能です。
V2Hの価格については、こちらの記事でも解説しています。
内部リンク:V2Hの価格と設置費用は?補助金情報やおすすめ機種も解説
設置にスペースが必要
V2Hの設置場所は、EVに充電しやすい駐車スペースの近くが最適です。スペースに余裕がない場合、設置が難しいこともあります。スペースを取らないコンパクトな機器もあるため、設置が可能かどうかは工事業者の判断を仰ぎましょう。
マンションやアパートなどの集合住宅では、個人の判断でV2Hを設置することはできません。ただし分譲マンションでは、住民総会で住民が承認し、正式な決定がされればV2Hの設置は可能で、補助金の対象にもなります(正式に決定されたことを証明できる書類が必要です)。
すべてのEVに対応していない
V2Hは、2025年7月現在、日本で販売されているすべてのEVやPHEVに、対応しているわけではありません。国産車の多くはCHAdeMO(チャデモ)規格に対応しているため利用可能ですが、テスラをはじめ、一部の輸入車、年式や仕様によってはV2H非対応の場合があります。または専用のアダプターや対応機器が必要となるケースがあります。
導入前には、所有車がV2Hに対応しているか確認が必要です。
用語集:CHAdeMO
用語集:Tesla
V2Hの設置で知っておきたいこと3選
V2Hを設置する際には、3つの注意点を抑えておく必要があります。ここでは、設置スペースについて確認しておくべきポイントを解説します。
EVの駐車スペースとの位置関係を考慮する
V2Hを設置する際は、機器と給電ケーブルとの距離やEVの駐車スペースとの位置関係を考慮することが重要です。多くのV2Hの給電ケーブルは約7.5mですが、車種によって充電口の位置が異なるため、駐車位置と接続場所を事前に確認しておきましょう。
メンテナンスのスペースが必要
V2Hには、メンテナンスのためのスペースを確保する必要があります。メンテナンススペースは、機器の両端からそれぞれ幅40cm以上、機器背面から奥行90cm以上、機器上部に50cm以上が目安です。メンテナンスは、原則として年に1回程度行う必要があります。スペースがないと機器の点検や修理がスムーズにできない可能性があるため、しっかり確保しましょう。
水没リスクを避ける
V2Hを設置する際には、水害対策を十分に考慮することが重要です。水害のリスクがある地域では、特に注意しましょう。水害リスクが高い場合には、機器を地面から少し離して設置するために基礎を設けることが推奨されます。基礎を設けることで浸水を防ぎ、安定した運用が可能になります。
V2Hの設置は、専門業者に相談し、地域の特性を踏まえた適切な設置方法を選ぶことが大切です。

【比較表】V2Hと普通充電器どっちがいいの?
V2Hを購入する際に知っておきたいのが、普通充電器との違いです。以下の表では、V2Hと普通充電器の違いを比較しました。
| V2H | 普通充電器 | |
| 価格 | 約90万円~180万円 | 約20万円~40万円 |
| 設置費用 | 約30万円~40万円 | 約5万円~15万円 |
| 補助金 | 地域によって適用あり 例:東京都 半額(機種ごとに上限あり、戸建住宅最大50万、事業用最大135万円) |
地域によって適用あり 例:東京都 ・通信機器付き設備→機器費:上限30万円/基 ・通信機能付き設備以外→導入費:2万5000円/基 |
| 充電スピード | 6kW前後(約2倍速) | 3kW前後 |
| サイズ | 幅50~60cm 高さ60~70cm 奥行25~35cm |
幅20~30cm 高さ30~40cm 奥行10~15cm |
| 非常用電源としての活用性 | ◎(家庭へ給電可能) | ×(給電不可) |
※価格・設置費用・補助金は機種や地域、年度によって変動します。
※普通充電器の設置費用は配線距離や工事内容により変動します。
V2Hは導入コストがかかるデメリットがあるものの、補助金額や充電スピードが早いというメリットもあります。非常用電源を必要とするかや、設置場所があるかなどを検討しましょう。
V2Hおすすめ機器一覧
ここでは、V2Hのおすすめ機器を厳選し、それぞれの特徴を解説します。
| メーカー
商品名 |
価格(税抜) | サイズ | 給電方法 | 保証期間 | 特徴 |
| ニチコン
プレミアム |
89.8万円~ | H860㎜×W810㎜ | すべての電化製品 | 5年 | 初期投資がリーズナブル |
| オムロン
マルチV2X |
160万円~ | パワコン H560㎜×W450㎜ ユニット H790㎜×W540㎜(セパレートタイプ) |
すべての電化製品 | 10年 | スペースに余裕がなくても設置できる |
| パナソニック
eneplat |
176万円~ | H1250×W420㎜×D210㎜ | すべての電化製品 | 15年 | 保証期間が長い |
(価格は2025年7月時点)
ライフスタイルや予算の状況に合わせて、適切なものを選びましょう。また、V2Hの国内シェア90%を誇るニチコンについて、以下の記事で解説しています。
内部リンク:ニチコンV2Hで停電時にも安心を|価格や補助金制度も解説
どんな家庭にV2Hはおすすめなのか
V2Hは、災害時の備えを重視する家庭、太陽光発電を導入している家庭、そしてEVを充電できる駐車場を持つ家庭に特におすすめです。各家庭のライフスタイルや防災意識に応じて、導入メリットが大きくなるため、詳しく見ていきましょう。
パターン①災害への備えを重視する家庭
地震や台風などの自然災害による停電リスクが高い地域に住む家庭には、V2Hの導入が有効です。EVの大容量バッテリーを家庭の非常用電源として活用でき、冷蔵庫や照明、スマートフォンの充電など最低限の生活インフラを数日間維持できます。
東日本大震災では、発生後2日目に70%、3日目に80%の世帯で電力供給が復旧しました。そのため、復旧までの数日間、V2Hを通じて電力が使えると有効な災害対策になるでしょう。V2Hは、災害時でも安心して生活を続けたい方に最適な選択肢といえます。
パターン②太陽光発電システムを導入している家庭
既に太陽光発電を設置している家庭は、V2Hとの連系で発電した電力をさらに有効活用できます。昼間の太陽光で発電した電気をEVに蓄え、必要なときに家庭で使うことで、電気代の節約効果が高まるためです。
V2Hと太陽光発電の組み合わせにより、年間最大12万円の節電につながる効果があるとされています。停電時も太陽光発電とV2Hを連系させることで、EVのバッテリーを活用しながら電力供給を継続できます。エネルギーの自給自足や家庭のレジリエンス向上を目指す方にもおすすめです。
太陽光発電システムとの連携には、パワーコンディショナーの出力やJET認証の有無など、一定の条件が必要となる場合があります。
パターン③V2Hを設置できるだけの駐車場を所有している家庭
V2HはEVと自宅を有線で接続するため、設置には専用のスペースが必要です。そのため、自宅に十分なスペースがあり、EVやPHEVを所有している、または今後購入予定の家庭に適しています。
なお、V2Hは駐車場が屋外でも設置可能な機種が多く、防水・防塵性能も備わっています。将来的にEVの台数が増える場合にも柔軟に対応できる点もメリットです。
V2Hのメリットに関するよくある質問
V2H導入を検討する際に多い質問として、「停電時の電力供給量」「EVバッテリーへの影響」「メンテナンスの必要性」などがあります。ここでは、それぞれ詳しく解説します。
停電時はどのくらい電力が使えるの?
EVのバッテリー容量や、電力の使用方法によって異なりますが、1~4日分を賄えると言われています。
ただし、エアコンやIHクッキングヒーターなど消費電力の大きい家電を同時に使うと、使用可能な時間は短くなる傾向です。停電時でも冷蔵庫や照明、スマートフォンの充電など、生活に必要な家電を中心に使うのがおすすめです。
EVのバッテリーに悪影響はないの?
V2Hによる給電や充電は、EVのバッテリーに大きな負担をかけるものではありません。V2H機器は車両メーカーの基準に則って設計されており、適切な範囲で充放電が行われるためです。
ただし、頻繁な過放電や過充電を繰り返すと、EVのバッテリーはわずかに劣化が進む可能性はあります。普通充電器や急速充電器を使用する際と同様に、過放電や過充電に注意することが重要です。メーカーごとにV2H利用時の注意事項があるため、取扱説明書やメーカーの推奨に従って運用しましょう。
メンテナンスは必要なの?
V2H機器を長期的に安定運用するためには、定期的な清掃が推奨されています。例えば、V2Hの呼吸性能を低下させないためには、給排気部分に汚れを貯めないようにすることが大切です。
特に、屋外設置の場合は、雨風やほこりによる影響を受けやすいため、防水・防塵性能を確認し、必要に応じて清掃を行うとよいでしょう。
なお、V2Hは水洗いも可能ですが、高圧洗浄機に耐えられる機種はほとんどありません。万が一、異常を感じた場合は早めに専門業者へ相談しましょう。
まとめ
V2Hは、家庭のエネルギーマネジメントを向上させる頼もしい存在です。V2Hを導入する際は、ご自身のライフスタイルや電気の使い方を考慮し、それに応じた活用方法を検討することが重要です。持続可能なエネルギー利用を実現する一歩として、V2Hの導入を検討してみてはいかがでしょうか。